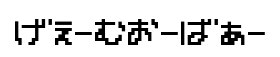2002年頃、不景気の中で起こった空前のパチスロブーム。そんなご時世に学校を卒業し新社会人となった若者は、もっぱら仕事帰りのパチスロに勤しんでいた――。
長編小説 / 社会ふ適合
「じゃ、研修がてら月曜から来てもらえっかな」
何気なく放たれたこの言葉が社会人としての最初の日を決めた。
楽しかった子供時代の終わり、責任と義務がつきまとう大人の世界へ、とうとう押し出される日がきたのだ。
時は平成14年、西暦にして2002年の3月に専門学校を卒業した。
折しも世の中はITバブルだか何だかが弾けて、どういうわけだか不景気らしく就職が困難だというご時世のようだ。
テレビをつければ完全失業率が過去最低だとか経営危機にリストラだとか、どれも感じの悪い言葉ばかりが飛び交っている。
しかし、それは先の話、まだ明日のことだ。
そんな子供時代最後の日も、いつものパチンコ屋に来ていた。打つ台もなくなりカズキの隣へ座って時間を潰す。
「あーあ、俺あしたから大人だー」
なんとなく思っていたことが口から出た。
「なんだよ、それ」
打ちながら視線を外すことなく、カズキは聞き返してくる。
「あしたからもう仕事始まるんだよ」
「はやくねー? まだ24日だぜ」
手を休めることなく、カズキは反応する。
「研修だとかいってた」
カズキの隣で時間を潰しながらも、どこかに大きく負けたままヤメた台がないかを目で探す。休日の店内は空いてはいないが、混雑しているというわけでもない。
カズキが肘で脇腹をついてきた。
ふり返ると、カズキがリールの辺りを指さしている。どうやら注目して見ろというジェスチャーのようだ。
黙って見ているとカズキは小さく力を込めてレバーを叩いた。わずかに遅れてリールが回り始め軽快な電子音が響く。リール上にある横長のドット液晶にはカエルがひょこひょこと息づいている。この台の演出の1つだ。
カズキは指で3を作ってみせてくる。どうやらこの演出が3連続起こったと言いたいらしい。この台は演出が連続すればチャンスなのだ。特に4連続ともなれば高確率でボーナスにつながる。3連続はその最初の通過点になり力が入るというわけだ。
さらにカズキはレバーを叩く。今度は願いを込めるようにゆっくり、と。
しかし、ただリールが回るだけでドット液晶に動きは見られずに終わった。カズキはがっくりとうなだれる。
あはは、と笑った自分に対しカズキはふて腐れた様子で黙々と回し続ける。
再び良さげな空き台が出ないか見回す。午後の店内はそれなりの客付きだが平日の5時過ぎのあの混雑ぶりと比べれば、この降り注ぐような騒音の中でも静かだと思えてくる。
「なんかなー、もっと社会人って遠いって思ってたのになー」
誰にともなくぼやいてみる。実際に2年あった専門学校での生活はあっという間だった。明日から自分が社会人というのがいまだに実感できないし、それをしたいとも思わない。
「おめーはいいだろ。専門で2年も遊んでたんだから」
すでに働いているカズキの言葉には棘ある。
「研修って1週間くらいあるけど給料でんのかな?」
思った疑問をぶつけてみる。
「でねーんじゃん。気になんなら聞けばいいだろ」
「聞けないでしょ。入ってすぐそんなこと聞いたらバカ扱いだし」
入って早々の新入社員が臆面もなくお金の話をすれば、非常識なやつだと白い目で見られるのがオチだろう。
「いいだろ、どうせすぐヤメんだから」
カズキは興味なさそうに言った。
翌朝、携帯電話のアラームで起きる。
7時35分、今日だけは特別だ。始業時間は9時だが常識的に考えて最初くらいは早めにいくべきなのだろう。
初出勤――、緊張と戸惑いの響きだが迎えてしまえば何のことはない。ただ足が重いだけだ。安いリクルートスーツに袖を通してアパートを出る。
車を走らせて会社へとむかうものの進みは遅い。同じく会社にむかうであろう車たちに阻まれて、止まったり進んだりを繰り返していく。
すっきりしない頭でこれからの仕事のことを考えるも、サービス残業、ボーナスカット、ベースアップなし、交通費が出ない――など、どこかで耳にしたケチ臭い言葉ばかりが浮かんでくる。
世は不景気らしい。通っていた専門学校でも就職先がないという形での危機感として伝わっていた。
それでも高いお金を払っているだけあって学校側は生徒に対し、次から次へと面接に行けとの指令を出していく。そして指示された通りに面接を受けに行ったら、あっさりと受かったというわけだ。
しかし、優秀な学生ではない自分にあてがわれた会社は大手企業であるわけでもなく小さな会社だった。当然だ。
そしていま目の前にたたずむのは砂利の駐車場に、大きな二階建てのプレハブの外観、昔ながらの町工場といったところだろう。
総従業員数もパートを含めても30人と小さな会社。ここが社会人としての主戦場、心もとないのは見たまんまだ。少し躊躇したが、ここで帰るわけにもいかず観念して中に入ることにした。
「まぁ、最初はどんなもんか見てちょ」
おかしな物言いをするのは工場長だ。ほりの深い、こげ茶色した肌の暑苦しいおっさんだ。面接が工場長と社長の2人だったから、それは知っていた。
工場長は、手当たりしだいに作業している者を呼びとめては名前を教え、どうぞよろしくを繰り返させる。何度も下げる頭の揺れのせいか、もう誰がなんて名前か分からなくなった。
覚えているのは、みんな親と同年代かそれ以上のお年を召した方々という事だ。高齢化社会の波がこんなにも差し迫っていたのかと、ちょっと気のきいた事を思ってみたりする。
大まかな案内と挨拶回りもすみ、次はいよいよ仕事内容かと思いきや工場長は勢いよく振り返ってこう言った。
「疲れたっぺ、お茶にすっけ?」
ついていくまま外に出ると自販機が見えた。その横には簡素な雨よけに野太い円柱の灰皿が置かれている。これでもかと吸殻が浸り、にじみ出た透明度の低い水に沈んでいる。
お茶とは業界用語でタバコが吸いたい、という意味になるようだ。工場長はポケットから小銭を取り出してコーヒーを2つ買って1つを手渡してくる。よりによって凄く甘いやつを。
「遠慮しねーでいいど」
いそいそと胸ポケットからタバコを取り出しながら言う。
「いや、タバコは吸わないんです」
火を付け、最初の一吸いに夢中の工場長の姿を観察する。
「ほうけ、マジメだね」
煙を吐いたあと呆けた顔で返事する。放心状態のようにも見える。どうやら工場長はニコチンが切れると落ち着きがなくなってしまうアレのようだ。
「今日いる人で全員ですか?」
急にしゃべらなくなった工場長との気まずい沈黙を素早く察知して質問を投げかけた。
「んにゃ、現場はあれで全員だ」
そう言って灰を地面に落とす工場長。
「若いおねーちゃんがいなくてガッカリしたけ?」
ニヤリと笑う工場長。何が嬉しいのか下がった目尻が、うれしそうな下卑た表情を作っている。この手の話に反応するとさらに喜ぶだけなので違う話題に切り換えることにした。
「一番若い人で何歳位なんですか?」
「んー、さっきいた山内くんが36歳で、あとはー、古川ってのが44歳ぐらいだったかなー」
なんとか思い出すように声を出す工場長。
「20代は僕だけですか?」
「そだね」
タバコを灰皿に落としながら工場長は言う。チッという蒸発音が小さく聞こえる。
「ずっと採ってなかったんよ。何人か中途で採ってみたけど使いもんになんねかったし、すぐ辞めっちまーんだ」
工場長は苦い過去を思い出すように眉間にしわをよせる。頭をかく左手にはなぜか捨てたはずのタバコが挟まっている。いつの間にか新しく取り出していたようだ。
「んだから、今年から若い人を採ろうっつう事になって……」
つまんだタバコが口元に届こうかという、すんでの所で止まる。口元からゆっくりと離れ、あらわになった口から言葉が漏れ聞こえてきた。
「どうだっぺ、やっていけそうけ?」
やさしくとも不安にもとれるトーンに真剣さを感じる。
言うべき事は分かっている。例え本心がどうあれ、ここで言うべき言葉は一つだ。
「はい、やっていけそうです」
出来る限りの健全さを演じて力強く答える。心にもない事を堂々と言ってのけた。
「ほうけ、そりゃよかった」
工場長は笑顔で答えた。ヤニで黄ばんだ歯が浮かぶ。
これから社会人としてやっていくことになった。さしずめ今日は人生の月曜日、昨日までの日曜が懐かしい。
2002年3月24日 +9000円
#1←前話・次話→3G目:最近のスロットは
(現在地:社会ふ適合/2G目:人生の月曜日)