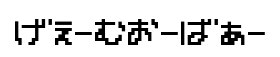2002年頃、不景気の中で起こった空前のパチスロブーム。そんなご時世に学校を卒業し新社会人となった若者は、もっぱら仕事帰りのパチスロに勤しんでいた――。
長編小説 / 社会ふ適合
鐘の音が聞こえる。仕事終わりを告げる音だ。
しかし、誰も手を止めようとはしない。自分だけが帰り支度を始めていた。
「お先に失礼します」
そう挨拶し作業場を後にする。パートのおばさま方はすでに帰った。残っているのは社員だけだ。
更衣室で着替え終わった頃には5時31分になっている。定時をそれなりに過ぎたが更衣室には誰も現れない。無駄な電気を消して会社から出た。
車を走らせ混雑する道を行く。この時間帯はいつもこうだ。目指す場所はそう遠くないのにいつも時間を取らされる。
しばらくすると、前を走る数台が吸い込まれるように入っていく場所が見えてくる。その一台となるべく、少し早めにウインカーをだした。
びっしりと車の並ぶ駐車場で僅かに空いた隙間を目ざとく見つけ、そこに滑りこむ。
車から降りて建物の方へと足早に向かう。入口近くともなると金属が降るようなこもった音が聞こえ自動ドアが開くとそれは爆発するように身を包んだ。
騒音をかきわけて進むと馴染みの後ろ姿を見つける。カズキだ。背を突いて注意を前から後ろに促す。
「ダメだ、でねぇ」
振り返るなりカズキは言い放つ。
「いくら負けてんの?」
「あー、2万くらいじゃね」
軽く言うカズキだが、その目は鋭い。頑張れと肩を叩いて、その場を後にした。
店内は流行りの音楽が大音量で流れ、何を言っているかわからないものの威勢がいい事だけはわかるマイクパフォーマンスが鳴り響く。照明を落とした薄暗さを裂くように色とりどりのレーザー光が踊り、スーツ姿のサラリーマンや作業着姿の客を中心に老若男女、多種多様な層が集まり電飾鮮やかなマシンを前にする。
そう、ここはパチンコ店。そのスロットコーナーだ。
日本中あらゆる場所にあり街中ならひしめきあっているのも珍しくはない、とても身近な遊び場だ。そんな活況を裏付けるように店内は客で溢れている。
そんな店内で今日の勝負に見合う空き台を探していると、今まさに目の前の客が席を立った。反射的にその台の履歴表示器であるデータカウンタを見上げる。
そこに記された履歴を確認し、下皿と呼ばれるメダル入れ部分に携帯電話を置いて台を確保した。履歴を見る限り、この台を打った客は大きく負けているはずだ。
台の良し悪しを決める調整段階は、最低となる『設定1』だろう。台としての性能に見込みはない。
残された幸運による勝ちも訪れる気配もなく、このまま続けても負けるだけ――、そう見限られて捨てられた台だ。
だが、この台でいいのだ。
着席して、財布から千円札の束を取り出し下皿に置く。その千円札一枚を台横にある備え付けの両替機、通称コインサンドに吸い込ませるとメダルがジャラジャラと落ちてくる。数にして50枚だ。おかしな話だが、これで当たるとは思わない。
それを右手ですくって台の下皿へと移していき数枚を手に取りコイン投入口に滑らすように入れる。そのすぐ下にあるレバーを叩くと3本のリールが回転し、少し遅れてストップボタンが受け付けるようになれば準備完了だ。
回転するリールはそれぞれに対応したストップボタンで停止する。左側のボタンを押せば左リールが止まり、そうやって全てのリールを止め終えると、これで1ゲームとなる。
これを繰り返していき一番大きな配当役であるボーナスを狙っていくわけだ。
だが、ボーナスは抽選による結果であって、こちらが意図したタイミングできてくれるような代物ではない。要は運任せとなる。
そんな中で、スロットを打つ客ができることは打ち方を工夫することだ。
それはボーナスが早く当選するように祈るオカルト的な工夫ではなく、ボーナス当選した場合の察知を早めたり、他に成立する役を取りこぼさないようにする効率的な打ち方のことだ。
具体的なやり方は機種によって異なるが基本さえ知っていればそう難しいものではない。
今打っているこの機種では、まず左リールの黒い図柄を狙い、次に中リールではなく、右リールを先に止める。その時点の停止型を確認して中リールを止める位置を決めるという手順になる。
これを繰り返し、いつくるかわからないボーナスを待つのだ。
打ち進めていくと最初の50枚はすぐになくなり、2枚目の千円札をコインサンドに入れて新たに50枚のメダルを下皿に移した。
当たらなければ千円分のメダルなど、ものの数分で消えていく。それでも千円をメダルに替えるのは、それなりに勝算があるからだ。
メダルも少なくなり、3枚目の千円札に手を伸ばそうとするが違和感を覚えて手が止まった。
目の前の停止したリールを見ると、何の図柄も揃っていない出目がある。いわゆるハズレ目がそこにあった。
「なんだよ。もう当たったのかよ」
どこからか出てきたカズキは憎らしそうにいってくる。
カズキの言う通り、このハズレ目は“当たり”だ。いつから見ていたのかわからないが、ぱっと見て気づくのだから流石だ。
「どうせバケだろ」
そう不吉な予言を言い放ちカズキは通路の奥へと消えていった。
このハズレであり当たりでもある出目はリーチ目と呼ばれるものだ。スロットはボーナスが成立しても対応図柄が揃うまでは何も起こらない。内部的にボーナスが成立しているが揃えられなかった場合に現れる特殊な停止パターンをこう呼ぶ。
さっそくボーナス図柄を狙うも揃ったのはBARと書かれた黒い図柄だった。
レギュラーボーナス……、この辺りではバケと略される残念な方のボーナスだ。ビッグと略される払い出しの多い方と比べてしまうと当たったのに損した気分になったりする。なぜバケと略されるかは知らない。
カズキの予言通りになってしまった。カズキからすればリーチ目の停止型からビッグかバケかの予想がある程度はたつのかもしれない。
あっさりと当たった自分へのあてつけの意味もあったのだろうが、カズキが悪態をついたのには理由がある。
この台はいったんボーナスに当選すると、それが連続する特徴がある。つまりは連チャンの期待ができるということだ。
連チャンすればメダルは加速的に増えていく。2連ならそれなり、3連なら及第点、4連以上ともなれば十分なメダルを吐き出すだろう。
その一方で、きっかけとなる最初の当たりが引けずに苦労することが多い。連チャンによるプラス部分は初当たりを悪くするという帳尻合わせの上に成り立つものになる。
だから、初当たりに手間取るのは台の仕組みからいって避けられない普通のことなのだ。そんな普通に出くわしたのであろうカズキは、さっきから通路を行ったり来たりして彷徨っている。
早い当たりは、そんな普通を覆すことのできる大きな価値を秘めたものだ。それがいま目の前にある。
身を包む騒音と大勢の客、可能性を乗せた3本のリールが揃って、ようやく今日がまわり始めた。
2002年_月 +7000円
表紙←前話・次話→2G目:人生の月曜日
(現在地:社会ふ適合/1G目:終わりの鐘)