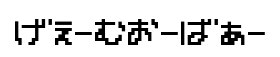不真面目な研究員が残したデータの行方
短編の一覧&作品設定 | 公開-2025/5/17
真っ白な天井と照明、完璧な空調、あくび以外を許さない静寂、整理されたデスクと並ぶワークステーションたち、ついでにドーナツとコーヒーがあったなら、ここは楽園であったのに、そこは惜しまれる。
だが、仕方ないのだ。
ここはとある大学の高価な機材が並ぶ研究室――、悩める人類を救世するため、その安息地の創造を任された最新の仮想現実研究の場なのだから。
「んー、暇だなぁー」
無駄にビブラートをかけて室内へと響かせる。
やることはない。お留守番が仕事なのだ。キャスターつきの椅子を転がしながら誰もいない研究室を見渡す。
視線の先には補助機器や太い有線でつながれたチェアユニットがある。
歯科診察用のシートを思わせる外観をしているが、これに身を預けると、あら不思議――、夢の世界へ飛び立てるというわけだ。今はまだその予定の段階らしいが……。
この仮想現実の研究室に誘われたのは、少し前のこと。
特に専攻したい分野などなく、ぼーっとしているところに声をかけられた。
話を聞くと、バーチャルリアリティーと人間の五肢五感をリンクさせる研究だという。口にすると怒られるが、要は仮想現実に人の全感覚を没入させるフルダイブ型のゲームを作っているようだ。とりあえずの単位の当てと所属を得られたのは僥倖だった。
とはいえ、まともな研究員として誘われたのではなく、高価な機材のある研究室の見張り役 兼 水増し要員としてだ。
だから、こうして誰もいない研究室で暇を持て余している。
一応は自分のデスクとPCは与えられてはいるが研究員ではない者には宝の持ち腐れだ。
高価な機材といっても高性能PCであるワークステーション以外は市販のVRゴーグルにVRグローブとフットセットを少し改造したもので、肝心の仮想世界を構築するのは有料ライセンスの3Dモデルアセットなど特別といえるものはほとんどない。
それでも限られた予算で研究を続けていくための大事なものになる。
特にVRゴーグルとグローブ&フットセットは転売効率の良いアイテムとして盗難被害に何度かあっているようだ。そんな世知辛い世相から研究機材を守る人員が必要となった。
だが、守るといっても強盗が押し入るほどの価値のあるものはない。
ゆえにただ暇と戦う日々が続いている。
そんな強大な敵を前に、とある攻略法を閃いた。ずばり、ゲーム制作だ。
研究室にあるワークステーションを使って自作ゲームを作り、それをPCゲーム配信プラットフォームであるStorm(ストーム)で販売する。上手くいけばそれなりの金銭が得られ、売れなくても別に損はない。
しかし、研究室の機材を勝手に使うのはまずい。何らかの名目とその許可は必要だ。
色々と考えた結果、3Dアセットモデルを使いやすいようにカスタマイズするという名目を思いつく。これならば、作業とゲーム制作工程が重なり無駄がない。
これを閃いた。天才か?
導入されている3Dアセットモデルは、ネットに転がっているフリー素材ではなく、有償ライセンスを持った正規品だ。さまざまなオプションと各種カスタマイズが標準で揃っていて高い品質と利便性を備えてある。
多くの個人ゲーム開発者たちが経費削減のためフリー素材を頼り、自力で調整やカスタマイズして、そのたびにバグやエラーと悪戦苦闘するはめになり、多くの時間をそれにとられ疲弊し、そして夢半ばで挫折していく。
有償ライセンス製品は、そんな無料の罠に陥らずにすむ神アイテムなわけだ。
実際にゲーム制作はズブズブの素人でもお金さえ出せば作ることが可能だ。あらゆる工程を省くことができ、並べるだけでそれっぽい形ができあがる。
もっとも、お金がないからこそ個人制作のゲームを作って売ろうなどと考えるわけだが、この研究室にはワークステーションと有償アセットモデルが揃っている。
知識はない。経験もない。だが、有り余る時間、そして高性能PCと有償アセットがある――、こんな恵まれたビギナーゲーム制作者がいるだろうか。石油王の息子か?
すぐさま許可を取り、作業を開始する。
許可はすぐ下りた。アセット使いにくいですね、調整しておきますか? バックアップはしっかりとっておきます、仮に不具合を起こしても有償製品はサポートばっちりです、と説明すると、「いいよ。よろしくね」の2つ返事だった。ちょろいものだ。
仮想現実の専門家とはいえ、ゲーム部分に関しては素人以下だ。
もっともダイブした先に表示される世界というだけで、この部分が研究の本質ではないのだから当たり前のことではある。
その点で未来の売れっ子クリエイター様はPCゲーマーとして幾多の無料クソゲーで遊んできた経験がある。その知見がここで活きるとは人生とはわからないものだ。
作業は順調に進むだろう。残すは、どんなゲームを作るのかという難問だ。
世に溢れるクソゲーをみればわかることだが、面白いゲーム、売れるゲームとはほんの一握りの世界。狙って作れるならまさに億万長者の天才クリエイターだ。
これについては諦める。面白いゲームを作るという荒唐無稽な挑戦はしない。
よって数で勝負する。
処理速度に優れるワークステーションと、簡単な調整ですむ有償アセットがあれば、とりあえず簡単なゲームを作ることはできる。
ミソはきちんとクリアできること。それでいて2時間は遊べるもの。この2つだ。
この2つの条件を満たしているなら、例えなんの面白みもない、アセットを配置しただけの世界をただ歩くだけのお散歩シミュレーターでも問題ない。
多くの個人制作のゲームはバグか難易度調整のミスで進行不能になりクリアできない。だから、クリアできるだけでも一定の評価を得る。
そして、2時間は遊べるようにすることは返金対象の条件から外れることを示す。要は2時間かかってクリアできるゲームなら、どんなにつまらなくても返金されず商品として機能する。つまり、お金が入る。
だが、昨今のプレイヤーはこの返金制度を悪用して2時間手前できっちりやめて返金申請をし、また新しいゲームを購入するを繰り返している。製作者サイドも2時間手前辺りで高難易度のウェーブ制コンテンツを用意して時間稼ぎしたりと、いたちごっこだ。
これから作るゲームは、これらを考慮したデザインになる。
別に難しくはない。
アセットを並べて進行ポイントを作り、終わりを設定する。あとは有償アセットに付属されているAIがある程度は作ってくれる。
業務用レベルのワークステーションを使えば、これらは一般的な個人制作勢と比べてはるかに早く生成され、よほどの金持ちでないと手の出ない有償アセットは使い放題――、地の利は我にあり、勝利は目前だ。
と思ったのもつかの間、ぞろぞろと研究室のメンバーが帰ってきた。
「おつかれー」
元気よく挨拶するのは、ユウリちゃん。ここに誘った張本人だ。
「オブジェクトの調整してくれるんだって?」
「うん、暇だし。スキルアップにつながるかなと思って」
「すごーい、向上心の塊だ!」
大げさに持ち上げてくれるユウリちゃん。この手に騙されて研究室へ入れられた。
「じゃあ、夜もよろしくね」
大きく手を振って見送ってくれるユウリちゃんに小さく手を振って研究室を後にした。
夜になり、研究室へおもむくとみな黙々と作業を続けている。
邪魔にならぬよう端の方にいると、ここの主である教授がこちらにやってきた。
「いやー、助かるよー。悪いねー」
そう教授は話しかけてくる。当初は怖い人かと思ったが、案外気さくな人だった。
「いやー、暇ですし。僕ゲームとかするから勉強のためにも役立ちますし」
「任せるよ。あとあっちの方も色付けとくから……」
急にこそこそと話し始める教授。『あっち』とは評価と単位のことだ。周知の事実とはいえ、おおっぴらにはできない関係なのでこんな風になる。
教授からしても、学生が自主的に居座ってくれるだけで、セキュリティ対策をしたり警備員を雇うようなことをして予算をさかなくてすむのだから喜ばしいはずだ。その上に手伝いまでしてくれるのだから願ったり叶ったりだろう。現に、この奇特な学生を見つけてきたユウリちゃんの評価は爆上がりだ。
教授の号令によって、研究室のメンバーは今日の作業を終わりにして帰っていく。
さて、ここからが本番だ。
大きな夢への第一歩、コツコツやっていこうかと思って席に着くなり嫌なものを見つけてしまう。
― がんばってね。夢にむかってGO!GO!だぁ。ゆうり♡ ―
ユウリちゃんが残したと思われるメモだ。ありがたいがプレッシャーになる。これを見えるところに堂々と置いていったのであれば研究室のメンバーにはすでに通達済みなわけだ。
名目のカスタマイズや調整はほどほどにするつもりだったが、こんなことをされてしまってはそれなりにやるしかなくなる。
諦めて手頃なアセットを調整してからゲーム作りに取り掛かった。
作るといっても待っている時間の方が長い。方向性だけ決めてあとはAI任せでほぼ完了となる。
AIが動いて作業を進めているのを眺めながら、業務用のワークステーション級PCでこの程度の処理速度しかでないことに感心する。
一般的なPCで作業した場合は気の遠くなる時間がかかるはずだ。普段触っているクソゲーたちも制作に要する時間と労力が相当にかかっているのを思い知る。
意外と大変だったんだなと、クソゲー製作者たちに心の中で謝辞を述べながら待っている間にStormの出品者用アカウントを作っておく。
今夜には完成するだろう。
早いようだが品質は良いわけがない。とりあえずの試金石だ。
これが最低限の出来なら、今後も期待できるだろう。なにせ、この速度で量産可能だからだ。大きく評価され人気ゲームとなり、たくさん売れるのは期待していない。どこかの暇人が試しに買って、そのまま返金し忘れる程度でいいのだ。
そんな展望を持ちつつ、傍らでやっている感を維持するための作業を続けていった。
売れない。全く売れない。
出品者アカウントに表示された数値は0ばかりが並ぶ。プレイされたことを示すわずかな数値も返金対応という形で終わっている。
売上なし――。
個人ゲーム制作は想像以上に険しい道のようだ。
わかってはいたが全くの0だとは思ってはいなかった。数人、いや1人くらいは返金を忘れて、それが売り上げになる予定だった。
「アホのくせに、これだけは忘れねーんだよな」
ゲーマーのケチさ加減につい愚痴がでた。
だが、事実は受け入れなくてはならない。次はどうするかだ。
レビューも一件もないので不評点もわからない。これでは改善案も浮かばないので、コンシェルジュAIにそのまま投げてみる。
【 該当ビデオゲームは以下の理由で不評と判断されてる可能性があります 】
・他の多くのビデオゲームと同じ構造で独創性に欠け、ユーザーから飽きられてるYO
・現在、Stormで競合するビデオゲームが170,41件あり、ユーザーが確率的に辿りつけないんでわ?デュフフ
・AIによる自動生成の疑いをかけられており、おすすめ表示や検索結果への何らかの制限を受けている可能性があるんだから!
・AIによる自動生成された作品をフィルタリングする機能によって、ユーザーから隠されている可能性はありまーす
誰が設定したのかおかしな語尾だが気になる点が2つ。
『AIによる自動生成』というワードと『AI作品をフィルタリングする機能』という聞き覚えのないものだ。
AIによる自動生成のデメリットはある程度予測していた。だが、フィルタリングについては知らない。Stormのプラットフォームには、そのような機能はないはずだ。
関連事項として『AI作品 フィルタリング』と検索してもらう。
すると、いくつかの参考URLが提示され、その抜粋文章の中で気になったものを覗いてみる。
そこには、氾濫する没個性のAI作品にうんざりした一部のプレイヤーたちが、事前にAI作品を避けるためのアルゴリズムとそのソフトをAIに開発してもらったと書いてあった。それほど精度は高くないらしいが、AIが作りがちな同時期に現れる似た構造物をクロールし、検索から排除することができるらしい。
これが他人の金儲けを脱兎のごとく嫌う『嫌儲(けんもうetc)』とカテゴリーされる掲示板に投下され、密かに広まったようだ。
調べてみると、このフィルタリングツールが使われ出したのは3ヵ月前辺りで、その広まりを考えれば、ちょうど出品時期と重なっている。
「こいつらほんと足を引っ張んのに全力だな」
嫌儲の精神には恐れ入る。だが、良い情報を知れた。
要は、AIによる自動生成と判断されないハンドメイド要素が強い作品なら勝負できる環境というわけだ。
そもそも手間暇かけたハンドメイドのオリジナル作品が、高速で生み出されるAI作品たちによって駆逐され、生成速度と数による勝負になっていた。それが、フリーツールとしてAIフィルタリング機能が出始まったことで環境が一巡したといえるだろう。
AIフィルタリングは誤算だったが、それでもワークステーションと有償アセットの優位は変わらない。
あとはAI生成と判断されない何かオリジナル性の高い構造や物語が必要なだけだ。
AIに……、と反射的に投げようかと思ったがぐっと堪える。
ここでAIに頼ると、似たり寄ったりのものになってしまう。作るのが結局AIだとしても、その出発点を任せるわけにはいかない。
顎に手を当て真剣に考えてみる。
だが、AIの提案を越えるような発想はでてこない。
何か奇抜な、あるいは局所的だがリアルな、それでいて誰もがとっつきやすい普遍的な何か――。そんな幻のような物語が浮かんでこないか頭の奥底を覗くようにどこまでも潜っていく。
ゆさゆさと揺らされるのを感じる。
「朝だよー。朝ですよー」
ユウリちゃんの声が聞こえて、ハッと目覚める。
モニターには3Dモデルのカスタマイズ画面が表示されている。助かった……、Stormの出品者管理ページのままだったら危なかった。
「すごいねー。そんなにがんばったんだ!」
褒め殺しのユウリちゃんには、そうでもないよと謙遜して答える。
その奥の方では他の研究室のメンバーが、クスクスと笑っている。バクバクの心臓と冷や汗を隠すため、そそくさと研究室を後にした。
眠気が吹き飛んだ頭で、そのまま構内にあるフードコートのカフェに入る。
コーヒーとドーナツを買って、ランチスペースで一息つく。
今後どうするか? 昨日から考えているが全く思いつかない。いっそ今までのAI任せのまま続けて、とりあえず出品だけは続けてみようかと考える。成果は出ないだろうが、出品を続ければ実績になるし、その間に何か思いつくかもしれない。
そんな風に頭を巡らせていると、むこうから見知った顔の二人組が歩いてくるのに気付いた。
どうも、と軽く挨拶するが、むこうは笑ったまま奥へと消えていった。
研究室のメンバーだが名前は知らない。むこうも同じだろう。
笑われていた気がするが、気にしてもしょうがない。むこうからすれば奇人変人の類だろうから。ユウリちゃんと教授ぐらいだろう。こんな自分を相手にしてくれるのは。
普段大勢でいる時の研究室はあまり知らないが、それでも水面下でドロドロとしたものがあるのは知っている。
教授は根回しや予算のやり繰り、研究の進捗、学生たちの監督指導と忙しくて少し病んでいる。ユウリちゃんはあんな感じだから研究室の中心にいるが、それを快く思わない者もいて、研究室のグループSNS以外のつながりはないみたいだ。さっきの二人組は付き合っているらしいが、片方が違うメンバーと仲良くしていたとか教授とも付き合っているとか噂が絶えない。盗まれた機材は、実はあいつが……、と疑いがあるやつもいるし、新参者でただいるだけの自分にユウリちゃんが良くしているのが気にくわないのかあきらかに敵対的な態度のやつもいる。
先進的な研究をする場とはいえ、しょせんは人間の集まりでしかない。
協賛してくれる民間企業からの視察と称した体験会が行われた時など、あるメンバーが自分を企業に売り込もうと担当者への執拗なアピールをして諫められ、かなり空気が悪くなったとユウリちゃんが珍しくぼやいていたことがあったくらいだ。
まぁ、人それぞれ色々あるにせよ、今はそれどころではない。
何か独創性溢れるAIにはマネできないものを考えなくては――、そう思考を巡らすと、足の方から電流が走ったような感覚を覚え、反射的に身がのけぞった。
熱い! どうやらコーヒーを溢したようだ。
席を立ってコーヒーがかかった部分をつまんで持ち上げる。場所的にふーふーするわけにはいかないので耐えるしかない。
やってしまったと後悔がわき上がるが、「いや待てよ」と急に頭が冴えてくる。
リアルな人間関係を再現した研究室シミュレーション――、これだ!
閃いたアイディアを忘れないようにメモしていく。
最終目的は、研究が政府主催のコンペティションで選ばれること。その道中は、問題巻き起こる研究室の運営をいかに上手く切り抜けていくか。経営シミュレーション要素も入れていく。研究員同士のケンカや恋愛もサブやノイズとして入れてもいいかもしれない。
予算、人員、研究のパラメータを作り、それぞれが規定値以上でクリア、下回るとゲームオーバーというシンプルな作りにして、数値を上げるためのイベントを多く配置すればいい。プレイヤーは予算を確保し、人間関係を円滑にし、研究の指揮をとっていく。コンペ優秀賞を真エンディングとして匂わせ、予算だけ達成した場合の終わりなど簡単だがマルチエンディング方式を採用する。
現場にいるリアルな研究室の様子を、面白おかしくシミュレーターとしてゲームにする。まだ出来てはいないが、手ごたえを感じる。
熱も冷めやらぬまま、さっそくその夜には取り掛かり始めた。
「最近よく話すようになったねー」
会話の途中でユウリちゃんにそういわれる。
「そ、そうかな……、ほら人見知りのコミ症だからさ……」
「えー、そうなのー?」
怪しむユウリちゃん。さすが感がするどい。
まさか自作のゲームで使うゴシップネタ集めしていますとも言えないので、なんとか誤魔化してその場をしのぐ。
ゲーム制作にあたり研究室のことをよく知る必要が出てきたので、よく質問をするようになったのが仇になった。しゃべらないやつが、少しでも話そうものならそれが変に積極的にうつったのかもしれない。バレたらここにいられなくなる。気をつける必要はあるだろう。
ゲーム制作の方は順調だ。
ただ、前のようにAI任せにできない部分が多いので苦労している。特に研究室のメンバーのそれぞれの性格は丁寧に作ってみたので、ちょっとした模擬人格のようで面白い。放っておくと他のメンバーとケンカが始まるので、もはや本人そのものではないかと笑えてくる。
有償アセットが優れているのもあるだろうが、なかなか満足がいくゲームができそうだ。
もう少し手を加えて調整をほどこせば完成する。出品までもう少しだ。
だが、ここで気を抜けば元の木阿弥だ。バックアップついでにフォルダ名も変えておこう。
『IF_2026』そう書き換えた。
もしも、を意味するifと、インターフェースを意味するIFを重ねたものに、今年の2026年をつけただけの簡素なフォルダ名にした。これをここの誰かが見ても、インターフェース用のオブジェクトのコピーか何かだと思って怪しまれる可能性は低くなるだろう。ダミーとして、part(particle)_2026や、obj(object)_2026など似たフォルダ名も用意しておいた。
あとは、Stormの出品者管理ページに使うための、作品の基本情報、キャッチコピーなんかを記載していく。
ー 仮想現実は君にどんな夢をみせてくれるのか ー
なかなかそれっぽいコピーだ。実際は仮想現実を作る人たちのしょーもない人間関係の現実を追ったゲームなのだから正反対そのものだが。
よし、と最後の不具合確認をAIに任せ、天井を見上げて成功への架け橋を思い描く。
翌日、足取り軽く研究室へと入るなり違和感を覚えた。
配置が違う――、いつもの場所にいつもの物がない。自分のデスクも、だ。
その瞬間、背筋に冷たいものが流れて、いっきに体温が下がり心臓の脈打つ音が聞こえてくる。
「な、なにかあったんですか?」
近くにいたユウリちゃんに聞いてみる。
「あ、おつかれー。大変だったんだよー。引っ越しー」
「引っ越し? ど、どこに?」
「隣だよ。言ってなかったっけ?」
疲れ気味のユウリちゃんはいう。
隣――、と聞いて少し安心したが、まだ心臓はバクバクいっている。
隣の部屋にむかうと、前の部屋と同じようなレイアウトのまま中央にチェアユニットがあり、その周りにデスクとワークステーションが並んでいた。少し広くなっただけのようだ。
ほっと胸をなでおろし、席へとついた。
PCを起動させ、データを確認するが見当たらない。そもそもデスクトップの配置も変わっている。
「これ、前使ってたやつじゃないんだけど……」
そうユウリちゃんに尋ねてみる。
「あれ? そうなの?」
「他のやつ確認してもいい?」
「いいよー。手伝おうか?」
そう快諾してくれるユウリちゃんだったが、見られては困るものなので大丈夫だよと遠ざける。
他のPCを立ち上げて確認していく。だが、どれも自分の使っていたものではない。それをユウリちゃんに聞いてみると教授と連絡をとってくれたようだ。
「あれみたい。これー」
そう言ってユウリちゃんが指さしたのは、中央に鎮座するチェアユニットにつながれた1台のワークステーションだった。
まずいことになった――。
他のPCならいざしらず、この研究室のコア部分とつながれてしまったのでは今までのように簡単に触らせてもらえないかもしれない。念のため、ユウリちゃんにこのワークステーションからアセットを移動させてもいいかと頼んでみる。
「色々と調整したばかりだから。あしたにしてだってさー」
ユウリちゃんののんびりとした声を聞いて、目の前が真っ暗になった。
翌日、教授がくるのを待って、いの一番でデータを移動、いやサルベージする決意で研究室に居座る。
「大丈夫? 顔色悪いよ」
心配してくれるユウリちゃんには、大丈夫だと強気にいって聞かせる。
ようやく教授が現れると、話す機会が訪れるまで辛抱強く待った。
「やあ、お待たせ。ごめんね。伝わってなかったんだね」
そう悪そうにいう教授に、データを移動して作業したい旨を伝える。
「いいよ。あっ、でも、元のやつはそのままにしておいて。ほら何をきっかけに動かなくなるかわかんないからさ」
教授は些細なリスクのことを心配していっているのだろう。
だが、こちらにしてみれば超ド級のリスクの塊が、すぐそこに置き去りになっているのをそのままにしておけと言われているも同然だ。納得できないが、それを上手いこと誤魔化す名目はみつからない。
しぶしぶコピーだけとって席に戻った。
例のチェアユニットにつながれたワークステーションの方をみると、教授が付っきりで作業している。隙ができそうにない。
どうするべきか? 夜にこっそりと消してしまうか?
よからぬ算段をたてていると、研究室に歓声があがった。
なんだと振り向くと、仮想現実への入り口となるチェアユニットにみんな集まって何やら喜んでいる。
吸い寄せられるように足を運ぶと、教授が嬉しそうにモニターを指さし、ほら!これ!と子供のように喜んでいる。どうやら仮想現実世界とチェアユニット、その補器のリンクが上手くいったようだった。
教授はひとしきり喜んだあと、平静を取り戻し咳払いの後に演説を始める。
「えー、みなさんのがんばりによって、ここまで来ることができました。今はまだ信号を拾って画面の中で認識できるだけですが、この向こうには確かに感じれるヴァーチャル世界があるはずです。今日は、その大きな一歩を、大事な一歩を踏み出せました。ありがとう」
そう力強く語る教授に拍手が注がれる。
「つきましては、このバーチャル世界へ実際に入りたい人を募集します! 誰かいないかな? 第一号だよ?」
そうおどけて教授は誘うが、みな顔を見合わせるばかりで名乗り出ない。
「教授が入ってくださいよー」
ユウリちゃんはそう提案する。
「いや、僕は外から調整しないといけないから……」
両手をぶんぶんふって拒否する教授。そんな教授の態度から、ますます誰も立候補しない雰囲気が流れ出す。別に危険はないはずだが変な装置をつけてそれを外から見られる滑稽さを思えば手はあげにくいだろう。
好機――!
「はい、ぼく入ってみたいです」
意を決して、そう言って手をあげた。心臓はバクバクのたぶん顔は真っ赤だ。
みな振り返り一瞬の静寂のあと教授が切り出す。
「おお! 入ってくれるの?」
「はい……、お、お邪魔じゃなければ……」
緊張し過ぎて声がろくにでない。
「うん、そうだよ。君がふさわしい! だってこの世界の外観は君が作ったんだから! みんなもいいよね? はい、拍手ー」
教授の号令とともに拍手が自分に注がれる。
「すごいじゃん。第一号だよ。パイオニアだよ」
ユウリちゃんも興奮気味にそう後押ししてくる。飛び跳ねて腕を引っ張るものだから体ががくがくと揺れる。やっぱりすごい力だ。
こうする他なかった。あのフォルダを、あの誰にも見られてはいけないデータを消去するにはチェアユニットにつながれたワークステーションのそばにいる必要がある。そのための口実は、これしかない。
さあ座ってと、うながされるが足が思うように動かない。
だが、もう逃げられない。
今ここで拍手をくれた面々を散々に茶化した危険なデータから己の未来を守るため覚悟を決めて歩み出す。
ガチャガチャと手足に機器をつけられ、改造された特別なVRゴーグルをかぶせられると音も視界も奪われる。
慣れ親しんだ現実から切り離されて一人ぼっちの暗闇に浮かんでいるようだった。
どうしてこうなってしまったのか。なにを間違ったのか。悪い夢なら覚めてほしい。誰にともなくそう願う。
みなの期待を一身に受けて出来上がったばかりの仮想世界へ沈んでいく。
そう、全ては『IF_2026』を永遠の闇に葬るため――。
機密データ/IF_2026 完?
作 ちよまつ(20230513)
#・次話→b2:中山峠
(現在地:短編/機密データ/I_F2026)