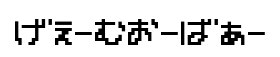VRと現実の間に漂いもたげるもの
短編の一覧&作品設定 | 公開-2025/10/13
20xx年――、人類は魂の救済を求め、究極の安息地となるヴァーチャルリアリティーの創造に乗り出していた。
だが、技術はまだ未成熟。仮想現実世界への道のりは彼のような アーリーアダプター たちの経験によるフィードバックを必要としていた、そんな時代。
「押したって!」
VRゴーグルをつけた男は吠えた。どうやらボタン入力を行ったのに、求めた反応がビデオゲーム内で起こらず不平を唱えたようだ。
「押しただろ! なんでパリィしねえんだよ!」
呼称『パリィ』、この時代のビデオゲームの特定ジャンルで多く見られた攻防一体行動の総称、またはその俗称。敵性体からの攻撃の際に生じるわずかな反撃猶予に対し、ジャスト入力を行うことで発動、敵性体への致命的なダメージと共にプレイヤーの自尊心をも回復させる顧客満足度の高い行動となる。
プレイヤー目線であれば、まさに花形と言えるテクニックであり、己の腕前を誇示する象徴性の高いギミックだ。
だが、そのパリィは失敗し、彼の分身は大型の鬼を模した敵性体によって地面に何度も叩きつけられ、まるでゴムまりが如くバインバインと跳ねていた。
「はぁー、クソゲー」
呼称『クソゲー』、古より伝わる呪詛。これを口にすることで責任の所在をビデオゲーム内、あるいは製造メーカー、ひいては社会全体に転嫁させることでプレイヤーのメンタルヘルスを維持する効能がある。
GAMEOVER――、彼の眼前に映る事実。
RETRY――、彼に強制される再出撃要請。
彼は動かない。ゲーミングチェアと呼ばれる座面の上で停止したままだ。
記録によると、彼はこの結末を27回繰り返している。時間にして3時間と47分、休憩は認められない。疲労軽減効果があるゲーミングチェア上での行為とはいえ、人体にとって過酷な環境下である可能性は高い。
なぜ彼はそこまで自身を追い込むのか。
彼が没頭しているビデオゲームはソウルライクと呼ばれるジャンル、その別名を『死にゲー』と呼称した。
死ぬことを前提にしたゲームデザインであり、彼が直面している現実は前もって予見される通常の挙動である。
自らに理不尽なストレスを与え、そこからの解放のカタルシスをえる狂気的、自傷行為的なジャンルともいえ、それはパリィの成功という象徴性を持って叶えられる。
その一方でゲームデザインを逸脱した結果に陥る現象も多く確認された。
今回の27回の失敗と、その連続プレイ時間は典型的な例と言えるだろう。
だが、彼は動かない。プレイを続行するか中断するかの間で揺れ動いている。
摩耗したメンタルとプレイヤーとしての矜持のせめぎ合いが肉体の停止という現象を引き起こしているのだ。
「ふー・・・」
彼は決断した。
天を仰ぎ、頭部に装着したVRゴーグルを外すためコントローラーをPCテーブルに置く。そして、見えない現実に置いてあるペットボトルを探すため、その手を伸ばし左へ右へゆらゆらさせている。
これは敗北ではない。単に喉が渇いたから。肉体という枷を持つ存在の宿命である補給行為のための致し方ない中断であり、戦略的な撤退であり、決して敗北という逃走ではないのだ。
「あ」
VRゴーグルをつけたままのペットボトルの捜索はすんでのところで失敗し、触れた指先の影響により倒れて現実世界をゴロゴロと転がっていく。
「・・・んだよー」
行方不明となったペットボトルが彼をVR世界からの一時撤退、その決断に至る決定打となった。
ため息混じりにVRゴーグルへと手が伸びる。
その両手がまとわりつく有線をかきわけて、その本体へと触れた瞬間――、異変は起こった。
ピキッ!
どこからか鳴った小さな小さな音。なんの音だろうか。
「あっ・・・あ・・・」
小さく漏れ出る彼の嗚咽にも似た声と共に、体が斜めに引っ張られるように動いていく。
口はへの字に折れ曲がり、足はつま先立ちで浮遊しようとする体をなんとか繋ぎ止め、手はバランスを保とうとアイアンマンの飛行ホバー状態かキューピー人形のポーズをとっている。
何かが導くのか、あるいはその罪から逃れるためか、体は彼の意思とは無関係に動き名状しがたく例えがたい姿勢を形成していく。
午前2時31分、齢33の独身彼女募集中、 ゲーミングチェア の上で奇妙なオブジェと化したまま朝を迎えるのだった。
「き、筋緊張性疼痛?」
「そう、筋肉が固まっちゃうやつ。首痛かったでしょ?」
白衣を纏う者は何かを見ながらそう言い放つ。
「げ、ゲームはできますか?」野球の石井一久選手が足の?ケガを負った際に開口一番、医者に聞いたのは「サッカーはできますか?」だったという面白エピソードより参考
「え? いや、できなかないけど・・・。しばらくは控えないと」
「ど、どうすれば治りますか!」
「え? ああ、運動して、よく寝て、ストレスをためないことかな」
とそっけない回答。
「あとね。VRモニターっていうの?あれみたいな、なんか重いやつ頭につけるやつは絶対ダメね。本当にゲームできなくなるよ」
白衣を纏う者は半笑いでいう。
ゲームができなくなる――。
ビデオゲームプレイヤーにとって、この世の終わりと同義といっても過言ではない言葉。おいそれと口にしていい類の言葉ではない。
乾いた人生に唯一残されたオアシス、日々労働に蝕まれる者を癒すささやかな調べ、連綿と続く思い出という名の轍、それを奪われたら何をもって生きればいいのか、大いなる羅針盤を失えば待っているのはただ虚空のみ。あってはならない。断じてあってはならない。そのはずだ。
家に帰るなりVRゴーグルを前に正座する彼がいた。
彼は考えていた。現実と向き合わねばならない、と。この廉価版とはいえ高リフレッシュレートを誇る魔法の鏡の奥に広がる∞のフロンティアに背を向けるわけにはいかないのだ、と。
それは使命感、あるいはなんかこう高尚なものかもしれない。
だが、無謀に突き進めば同じ過ちが待っているだろう。それは勇気ではなく蛮勇、ここは無策をもって突撃すること相容れん。是非もなし。
彼はまずは情報収集を開始する。
敵を知れば百戦危うからずと『VRゴーグルが重くて首が痛いんだけど』とAIに聞く。
- 休憩頻度とストレッチのルーティン化。連続プレイ時間を30分〜1時間ごとに区切り、必ず休憩を取ることを習慣化してください。休憩中は、首や肩のストレッチ(特に前後・左右の側屈運動)を数分間行うことで、疲労の蓄積を防ぎますよ。
- VRデバイスの上位モデル・軽量版を導入。現在使用しているデバイスより軽量な製品を使用することで身体への負担を軽減できます。また、有線式ではなく無線式のモデルの方が軽量かつ取り回しも良い傾向にあります。ただ、コスト面の懸念は残るかも。
- VRデバイスを使用せず通常モニターを使用する。これが一番、現実的な案ですね。既存のVRデバイスはどうしても重量の問題がつきまといますからね。通常モニターでも十分にプレイは可能ですよ。
ゲームは1日1時間――、余計なお世話だと憤慨しつつ彼は提示された案を真剣に考えてみる。
1の案は悪くないが、もう遅い。即効性がないと判断する。
2の案は――、そんな金なし。無理だと断念する。
やはり3の案が現実的だろうと、PCテーブルのモニターへと視線をうつす。
『やすぅーい!』ことを売りにする名物通販番組で紹介される7インチ大画面モニターの3倍以上の大きさを誇るが、VRゴーグルの眼前いっぱいに広がる光景と比べると頼りなく映る。
 夢くらぶが誇る”7インチ”大迫力・大画面でーぶいでープレイヤーに度肝を抜かれた者は多いだろう。さりげなく行われる商品を大きく見せるため社長と助手を小さくする名采配が光る
夢くらぶが誇る”7インチ”大迫力・大画面でーぶいでープレイヤーに度肝を抜かれた者は多いだろう。さりげなく行われる商品を大きく見せるため社長と助手を小さくする名采配が光る
今さら通常モニターに戻る・・・、その事実を受け入れられない彼は、床に置いたVRゴーグルへと手を伸ばす。
「いてて・・・」
だが、動いたことで彼の首のバランスは崩れ、警告シグナル発してその手を諦めさせた。微細な姿勢変化をも許されないほど彼の首は危うい状態なのだ。
「はあ・・・」
彼は諦めて、首を刺激しないよう姿勢を保ったままゆっくりと立ち上がり、恐る恐るゲーミングチェアに腰掛ける。
PCを起動し、表示設定をVRゴーグルからモニターへと変更。GAMEOVER表示のまま止まっていたビデオゲームの再開を試みた。
なんとかプレイはできる。だが、パリィどころではない。基本となる移動や攻撃にも違和感を覚えてままならない。表示されている世界の見え方が違うことへの影響に戸惑いながら、彼は必死に順応しようと足掻いていく。
30分もすると動きはスムーズになり、一見して問題ないようにみえた。
だが、彼の表情は暗い。ゲーマーの知見が、この状況の問題点を冷静に分析していたのだ。
VRゴーグルと比べ通常モニターでのプレイは、そのまま視覚情報の縮小につながり、敵攻撃の初動の見極めがむずかしくなること。
VRゴーグルと比較して左右上下の視点移動をコントローラーで行う必要があり、そのぶん動作や反応が遅れること。
特にこの2つに直面する。
これは繊細かつ素早い反応を求められるアクションジャンルのビデオゲームでは致命的といえるだろう。一方で、シミュレーションやRPGジャンルであれば支障なくプレイ可能であった。
彼はその事実を受け入れて静かにログアウトとする。
「ふー・・・」
彼は目を閉じ、己が首の状態を確認する。ゆっくり、ゆっくりと動かし、どこまで動かせるか、どの方向なら痛みが少ないのか確かめていく。
テッテッテッテテーテテ~ テッテッテッテテーテテ~♪
突如、某ピエロのパチスロのBGMが突如鳴り響く。彼の通信端末に設定されている受信音だ。
それは彼を驚かせると激痛も一緒に運ぶ。痛みをこらえながら通信端末を操作し、「はい」と返事する。
「よう!カゲノモノもうクリアした?今作、難しくねー?おれ6番目の鬼倒せなくて途中でつまってるわ」
端末からデリカシーのなさそうな声が響く。
「あー、おれはその先のやつまでいったとこ・・・」
「もう倒したのかよ。どうやった?最後のラッシュかわせねーよ」
通話先から聞こえる『最後のラッシュ』とは、死にゲーに搭載されているシステムのことだ。主にボス級敵性体の体力がわずかになると、それまでの攻撃頻度、行動パターンを変えて簡単には倒せないようにするための最後の障壁として機能する。
「あー、初段は回避してから回り込んで2撃目をやり過ごして、3撃目をパリィすればいけるよ・・・」
声を出すと首に振動が伝わりに、ジクジクとした痛みがデリカシーのない声と共鳴する。
「2撃目回り込むのかー。でも、回り込む隙なくねー?」
確かに何度も繰り返す中で上手くいった時に強引に押し切ったので、それが再現性あるパターンなのかを確かめたわけではない。だが、それを詳細に説明するほど余裕のある状況ではなかった。
「攻略でもみればいいじゃん・・・」
「えー、そんなの見たら負けだよ。お前まさか見たの?」
「見てねーし・・・」
「今度さー、みんなでレイドベントあるけど、お前もくんだろ?それを見してくれよ。みんなに確かめてもらうわ。逃げんなよ。じゃあな」
そういうだけ言ってデリカシーのない声は去っていった。
逃げんなよ――。誰にものを言っているんだと憤慨しつつ、デリカシーなしマンより先に進んでいるという事実が彼を喜ばせた。
だが、ここで彼は気づく。
首の痛み、VRゴーグル、パリィ、レイドイベント、みんな、――逃げんなよ。
彼の顔色は文字通りの青となった。
VRゴーグルを装着できない状況で、デリカシーなしマンによって吹聴された攻略、華麗な回避とパリィを披露できずに無様を晒せば、「はったり野郎w」とそしりを受けること明白。このままではプレイヤーとしの名声は地に落ちるだろう。
せめて、あいつにだけ打ち明けて先延ばしにしてもらうか?そう彼は考える。
――ダメだ、と今はふれない首をふる。
やつに通常モニターでゲームをしているのがばれたら「テテテ、テレビでVRwwww」と超絶バカにされるにきまっている。彼は地上の何よりもそれを恐れた。
どんなにリアルが底辺だとしても、この世界で軽く見られることだけはあってはならない。そう言わんばかりの彼がいる。その表情は鬼と化していた。
あの日から彼の日常は一変する。
まずはドラックストアへ向かい新製品を謳う市販薬など見て回り、今度は〇〇式マッサージ店へと入ると、ただ苦痛を味わい帰宅する。そして、自宅では通常モニターを使用した例のボス戦研究に励む。
VRゴーグルを使用せずとも華麗なパリィを披露できれば、彼のゲーマーとして尊厳は保たれるのだ。節制と研鑽を重ねる姿は神々しく、人類の在るべき姿であった。
アラームを設置し、定期的な休憩を取り、ボスの初動を見極め、再現性の高い攻略パターンを構築し、とどめのパリィへの導線を着実に紡いでいく。
その間、彼の首は動かない。
貯まりに貯まった有給休暇を使用し、彼は労働からしばしの解放を約束されている。だが、彼はその時間を建設的とは程遠い作業へと割り当てていた。
ピピピピー
休憩を知らせる合図。彼はただ目をつむる。これが彼の休憩なのだ。
いまだジクジク痛む首という脆弱な存在を確かに感じつつ、彼はある答えを出そうしていた。
「むずすぎー・・・」
彼はつぶやくようにいう。
土台無理な話だったのだ。VRデバイスの使用を推奨とするビデオゲームに対し、通常モニターで華麗にパリィを決めるという挑戦自体が。
彼は目を開き、新たな覚悟を決める。
VRゴーグルをつける――。
現状を打破する唯一の手段。遠回りして戻ってきた原点。答えはすぐそこにあったのだ。
彼はPCテーブルの隅に追いやっていたVRゴーグルを手元に引き寄せる。ゆっくりと、ゆっくりと持ち上げ頭部へと運んでいく。
有線はつけない。まずは装着が最優先事項だ。
痛い――。彼の首はそう訴える。
細心の注意を払いバランスを崩さぬよう大きく息を整える。
一見すると成功かに思えた。彼はVRゴーグルをつけている。ゲーミングチェアの堂々と座っている。
だが、彼は動かない。いや、動けない。
装着はできた。しかし、とてつもなく危ういバランスの上に生かされているに過ぎなかったのだ。その証拠にコントローラーすら持つことできず、ただ怪しいデバイスをつけただけの肉塊がそこにあった。
VRゴーグル――。この時代のVRデバイス呼称のひとつ。主に頭部に装着するヘッドマウント型ディスプレイ及びその周辺機器の中で、一番の要件となる映像投影部分が、スポーツや作業などのアクティビティ時の眼球保護装具のゴーグルと形状が近しいことから、比較的に占有率の高い呼称といえる。
件の彼は愛着を込めてVRゴーグルと呼んでいるが、人が変わればより広義となるVRデバイスとなり、また人が変わればメーカー独自の製品名となるだろう。通はヘッドマウント型ディスプレイの略語であるHMDを使用する例もあるが、これは同時代にあった接続規格のHDMIと語感が近く、高確率で混同が起こっている。
そう、非常にややこしい。
さらに各メーカーの商標登録、そのブランド規格によっても名称が変わり、製品全体から一部部分だけを指す名称が混在して正確性に欠ける言葉であるが、聞けば『あー、あんなやつね』として定着している。
だが、それらが問題になることはなかった。
それよりもはるかにフェイタルな問題、このVRデバイス自体の普及を阻むほど大きな技術的障壁が、その原初より存在したからだ。
重量――、つまり重さ。ウエイト。
他にも見えすぎるがゆえのモニター酔いや、有線ケーブルの煩雑さ、コンシューマー機としての価格帯の問題、供給されるソフトの選択肢の少なさなど課題は山積であったが、そんなものは重量というそびえ立つ壁の前には児戯に等しかった。
そして、この問題が根深いのは単にデバイス重量という解決可能な課題だけにとどまらない点だ。
そう、首。人体の首。ネック。
人という興味深い生物は、なぜか極限まで脆い部位を後生大事に進化してきた。
体と頭部をつなぐ要所でありながら、体毛も薄く、頸動脈は薄皮一枚、失う体温比率も高く、耐衝撃性もあるとはいえない。これが工業製品であるなら即リコール、設計責任者は糾弾されるだろう。
感覚器官を旋回させるため索敵能力は認められるものの、すでに周囲を警戒するような生活環境になく、左右にいる同族への配慮を欠かさないというコミュニケーションを円滑にする装置にしてはデメリットが大きすぎる。
音声を出す器官も内蔵、エネルギー源を取り込むための食道と酸素と二酸化炭素のガス交換する呼吸器道がよくばりセットで配置され、誤嚥という致死性の誤作動をひんぱんに起こしている。
フェイルセーフが確認できず、エラーが起こった際には筋線維の反射で強引に解決するというプロセスがとられている。
人体において司令塔である頭部、現実空間への力学的干渉をおこなう手足、それらを円滑に接続し、情報を伝達するという極めて重要な役割を持つにもかかわらず、これほどまでに脆く、矛盾に満ちた構造を持つ頼りない部位になぜに依存し続けなければならないのか。
神をも目指す人類にとって、その首のあり方が問われる日も遠くないだろう。
彼はまだ動かない。
首が痛いのだ。その首が痛むのだ。
すぅー、と息を吐き、呼吸を整えると、再びその手をVRゴーグルへと伸ばす。
両手で支えるようにVRゴーグルを持つと痛みが和らいだのだろう。表情が和らぎ、ひと時の安寧を得たようだ。
ピピピピー
再びのアラーム。彼の身体はビクッと反応し、次の瞬間には押し寄せる激痛に顔を歪ませるのだった。
翌日、彼は通常モニターの前にいた。
頭部にVRデバイスはない。ビデオゲームも起動せず、何かを見つめている。
『民間療法』――、検索欄に記述された文字。彼は禁断の世界に足を踏み入れていた。
科学的根拠のない裏の医学、経験則と勢いがものをいう魔境の住人たちが研究する闇の治療術、インターネットの奥底にうごめく霊感施術師に接触しようとしているのだ。
彼は探している。
だが、反応はない。
竜神、守護霊、電磁波、ベクレル――、文字にするとあまりに信用できないテキストコンテンツが並ぶ様子をみて、藁をもすがる状態である彼でもかろうじて理性を保てているようだった。
彼は諦めたのか次なる行動に出る。
今度は動画を見始めたのだ。
配信プラットフォームの検索窓に『首 痛い』と直球勝負で挑んだ。
彼は眺めている。
だが、反応はない。
先ほどとは違い今度は、医学博士や医学療法士、整体師、鍼灸師などさまざまなエキスパートのサムネイルが並んでいた。
どれも再生数も多く、確かな出自の人物たちの科学的根拠に基づいた解説だろう。
だが、彼は動かない。
また検索窓にカーソルを合わせ、今度は『首 医者VS民間療法』と入れていた。変わったワードチョイスだ。
――動いた! 彼が動いた。
微動だにしなかった彼が、わずかだが動いた、そう見えた。
彼の視線の先に映っているのは『♡首ボキボキ体操♡』というピンクと丸みを帯びたフォントで手作り感漂うサムネイル。
彼は見る。この動画を。真剣に。
再生された先には、ベッドに仰向けに寝かされた患者、タオルを持った施術者、タオルは患者の顎に引っ掛けるようにして添えられ、施術者はそれを左右にリズミカルに引き、患者の頭はグワングワンと揺れる。
ボキボキと音が鳴る。首から出ているのかは定かではない。フェイクの可能性もある。患者は目をつぶりされるがままだが、その表情に苦痛はみられない。
生物が発するにしては奇妙なボキボキ音をたて1分ほどで施術は終わった。
『いかがですか?』、『すごいです!嘘みたい』という芝居が始まり、施術の効果が強調される。そのやり取りの中に、治った、改善した、痛みが引いた、というワードは含まれていない。
彼は動画を閉じた。
疑いから見切ったかに予測されたが、彼の次の行動にそれは覆される。
『首 ボキボキ』――、検索窓に高速で記述されたテキストデータ。彼はさらに危険な領域へと足を踏み入れたようだ。
人体の要所である首と、何かが折れることを示すボキボキという擬音。単純な関連性を考慮するれば推奨されない組み合わせであるが、その検索結果には多くのサムネイルが並んだ。
3分で完全に治る、強烈昇天マッサージ、痛みよ永久にさらば、地獄から天国へ、などキャッチーな文言が羅列されており、次いで完全無料、タダとなぜか金銭の有無を匂わせるワードも添えられていた。
動画配信プラットフォームの検索は通常の広域検索ではおよそヒットしないであろう類の情報が提示されることがある。
その入り口を見つけること自体が困難でニッチな情報だが、ひとたびその門を潜れば花が開くがごとく次々と新たな情報が現れ、その奥へ奥へと誘いこんでいく。
彼はじっくりと確かめるようにスクロールし、その刺激的なサムネイルを眺めていく。
簡単に飛びつく様子はない。
吟味しているのだ。
期待、渇望、興奮――、彼の内面に渦巻いていると予測される感情。だが、彼は慎重だった。ここ至ること自体が理性的とは言い難い経緯ではあるが、彼は最後の一歩、その一歩を理性的に判断しようとしている。
そして、無数のサムネイルをかきわけて彼は辿り着いた。あの動画へと。
動画の再生が始まると、黒い道着をまとった中年の男性とゲストがシステマという格闘技の極意について話している。その内容は、力みを排除しリラックスがかかせないこと、筋肉だけでなく精神の脱力が必要で、武術にあって破壊の否定こそがテーマだと、哲学思想的なものを和やかなに解説していた。
ひとしきり話が進むと、黒い道着を纏った指導者であろう人物が棒を使い天井の滑車へとロープをかける。
吊るされたロープの先端には医療用の器具だろうか、顎の下から頭頂部や後頭部を覆うサポーター、首を固定するコレクトウェルのようなものを組み合わせた奇妙な装具がついていた。
指導者は助手を呼びつけると、床に座禅させ、その頭部に装具をつけていく。
装着し入念なチェックが終わると、指導者は「じゃあ引っ張るね~」と軽く一声かけるとロープをゆっくりと引いていった。
座禅を組んだ助手の体が浮く。
床から数センチという高さではあるが確かに浮いている。
驚くべきことに宙に浮いた身体とロープの接点は頭部、いや首にしかない。
座禅を組んだまま浮いた助手は「あー、スゴイっす」と感想を漏らす。その表情に息苦しさや苦痛は認められなかった。ゲストは驚き、「大丈夫なの?」と心配の言葉をかけるが「ぜんぜん苦しくないっす。気持ちいいっす」と助手の様子に異変はなかった。
推定60キログラム以上はあるであろう成人男性の身体が首だけを支えに浮いている。
彼はじっとその様子を見守り、動画を最後まで視聴し続けた。
翌日、彼はホームセンターの資材館にいた。
単管パイプや接続クランプ、その他関連備品を選んでいく。最後にロープを売り場に訪れ、1つ1つ手にとってはその感触を確かめていく。
特に伸縮性を気にしているようだ。伸びすぎず、硬すぎず、程よい伸縮性を求めてかれは小一時間、ロープ売り場で商品を引っ張っていた。
店員に不審に思われつつ買い物を終えて家に戻ると、ちょうど配達員が不在票を書いているところに出くわす。
彼は名の名乗り、荷物を受け取ると買ってきた大量の単管パイプとクランプを室内へと運んでいく。動かない首での作業を強いられている彼だが、不平も言わず黙々と動き続けた。
全ての荷物を室内へと入れると、追加料金を支払ってまで即日配送に指定した段ボールの中身を取り出していく。
あご保護用サポーター、医療用コレクトウェル――。
2つのアイテムを手に入れると左右の手に持ち見比べる。そして、室内に転がる単管パイプを眺め、彼は目をつむると完成予想図を思い描く。
そして、滑車を買い忘れたことを思い出していた。
「なんだよ。ログインしてねーじゃん。コソ練してんのか?」
例のデリカシーなしマンからの連絡が届く。コソ錬とは、ゲーマー用語で『陰でコソコソ練習している』という嘲笑を含んだ言葉だ。
彼は無視して作業を続ける。
ここ数日で彼の部屋は別物へと変貌していた。
部屋には単管パイプで作った構造物が天井に張り巡らされ、トラスト構造により補強されている。そして、中央には滑車が吊り下げられ、ロープをかけられるの待っている。この滑車はセルフジャミング機構があり、一定の負荷で停止するはずだ。
彼の手には試行錯誤の末に作り出されたあごサポーターとコレクトウェルの改造品と、3本の異なる素材で編んだロープがあった。
ロープを滑車にかけると、体重をかけグイグイと引っ張って伸縮性を確かめていく。
彼の全体重を預けた際に絶妙な伸縮性を発揮させるようにゴム製素材と通常素材を組み合わせたお手製のロープだ。その先端には“何か”を引っ掛けるための金具が取り付けてある。
”何か”、それは彼が最も苦心した器具、己の身体と吊るされたロープを接続する特別な装置、1人のゲーマーを真の意味で仮想世界へと没入させる救済としての窓口。
彼は命名する――、安心首だけ宙吊りくん、と。
これは首の固定器具だけを指す言葉ではない。単管パイプ、滑車、ロープ、そして彼自身の身体をも含む、人機一体を指す極めて概念的なものである。
完成した究極のシステムを前に、彼は準備体操を始める。
全身をゆっくりと動かし、少し動くようになった首を傾け、その痛みを確認をしていく。呼吸を意識し、まるで今現状の首と語り合うかのように丹念に丁寧に動かしていく。
準備が整うと、安心首だけ宙吊りくんを装着して座禅を組む。
その姿は修行僧を想起させた。
ロープの先端と安心首だけ宙吊りくんを接続し、VRゴーグルをうやうやしく――。(警告:この手順は倫理規範と安全性を著しく損ねています。本記述は安全プロトコル【S-3.2】に抵触するため、以降の描写は厳格な制限を受けます。細部を省略し、模倣性排除のため非連続的な情報に差し替えを実施)
なんやかんやあり、彼は宙に浮く。
「はぁ~」
成功の雄叫びにしては情けない声であったが、廉価版の重いVRゴーグルという呪縛から解き放たれたことを示していた。
この浮遊はまるで重力という逃れがたい現実を克服したような錯覚すら感じるほどであったとされる。
かくして彼の試みは成功に終わった。
彼は約束していたレイドイベントに参加し、華麗とは言わないまでも数回の失敗だけでパリィを決め、同行者たちへの面目を保つのだった。
その際の彼が成功を誇示することなく非常に謙虚な態度であったことが同行者たちに好印象を与え、図らずも大きな称賛を得る。
彼のように独自のデバイス開発に乗り出す者は珍しいわけではない。おそらくは同時代に一定数いたであろう アーリーアダプター たちの記録に残らない、技術史の闇に埋もれた試行錯誤の一幕なのだ。
だが、この彼の様子に疑念を持つ者がいた。
そう、あのデリカシーなしマンだ。
持ち前のデリカシーのない気質により、チートを疑い追求しようと彼の家にアポイントなしで赴いた。
「なんだこれっ!?」
デリカシーなしマンは驚愕する。眼前に広がるのは異様な光景。室内に単管パイプの構造物があり、吊るされたロープと怪しげな器具。およそビデオゲームをする部屋とは程遠い儀式の跡がそこにあったからだ。
「お前おかしいよ!」
デリカシーのない声を投げかけるが、部屋の主である彼は微笑して受け止める。
そして、余計なことを言わず、彼はデリカシーなしマンに安心首だけ宙吊りくんを勧める。
「やだよ!こんなのつけんの。ほんとに大丈夫なのかよ!」
デリカシーのない声とは裏腹に目立った抵抗もせず、されるがままに件の器具を装着させられてしまう。
「ふぁ~、なんだこれ!超すげー!!」
デリカシーのない声は歓喜する。この者もまたゲーマーとして首の不調を潜在的に抱えていたのだ。
浮遊する感覚、首への負担がまるで消えたような心地良さ、重力すら克服したかに思える別世界への扉を開いた革新的体験、安心首だけ宙吊りくんの効果が世に認められた瞬間といっていいだろう。
その後はデリカシーなしマンによって瞬く間に吹聴され、連日彼の家に首に問題を抱えたゲーマーたちが押し寄せるようになる。
ほとんどの者は疑い、その危険性を訴えるが、一度使用すると手の平を返し褒めたたえるのだった。
彼はこれを自分の発明とはせず、ロシアの軍隊格闘術であるシステマの修行兼リラックス法であり、由緒あるトレーニングだと説明していく。より安心してもらえるように、この着想を得た動画を見せようと思ったが、なぜか削除され見ることは叶わなくなっていた。
「これ動画にとってアップしよぜ!」
デリカシーのない発想が持ち上がる。
そう、もう彼の手を離れ安心首だけ宙吊りくんは動き出していく。
彼はゲーマーネックと呼ばれる悩みに・・・、人と機械がつながることによって生じる苦しみに・・・、一筋の光明を与える者として歩み始めていたのだ。
遠い将来、VRデバイスが首の負担から完全に切り離される時代まで、安心首だけ宙吊りくんは名を変え、姿を変え、 アーリーアダプター たちを救うだろう。
笑顔で正しい首吊りを教える彼だが、そう遠くない日にSNSで大炎上し、システマの呼称を巡り訴えられ、さらには建築基準法、消防防火法違反で書類送検されたり、女性関係で裁判になって損害賠償を請求されたりと、その活動には多くの困難が待ち受けている。
そして、遠い遠い日にVRデバイスが人間の身体への負荷を求めなくなった時代になると、今度はあるべき苦痛と身体性への回帰、人間性を機械から取り戻そうとする反VR運動が巻き起こり、原始的な負荷と解放を再現するための『聖なる儀式』として歴史の表舞台へと現れる。
彼はその創始者と呼ばれ、彼を称える多くの信徒が教義に従い、ひとつの巨大なミームとなって、とてつもないトラブルを引き起こすことなど知る由もない。
今はただ嬉しそうに皆の首を吊っていく彼の姿が――、そこに確かにあった。
その首のあり方 完?
作 ちよまつ(20251013)
#d4←前話・次話→b6(B2):ナカヤマトウゲ
(現在地:短編/その首のあり方)