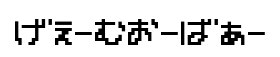山間で起こる怪異に巻き込まれた若者の恐怖体験
短編の一覧&作品設定 | 公開-2025/5/17
薄暗い峠を走る1台のバイク。落ちた葉や木々の端をタイヤが咬み、ときおり異音を発してはスピードを緩めろと警告してくる。
対向車もなく、ひたすら生い茂る木々に埋もれたこの峠道を進んでいく。
もうすぐ陽が落ちる。
それまでには辿りつけるはずだった目的地はここにない。道に迷うはずもなく、ただ一本の峠道を進んできただけだ。
この峠に入って、どのくらい走っただろうか。
バイクのバッテリー残量も心もとなくなってきた。まだ余裕はあるとはいえ、こんなところで立ち往生してしまったらと嫌な想像が膨らむ。
その後も坂をのぼったり下ったりを繰り返すが、いっこうに峠を抜ける気配がない。
ずっと似た景色が続く、さっきみたような木々の様子、ブレーキをかける傾斜の感覚、一定間隔で現れる標識、既視感がある緩やかなカーブ――、まるで同じところを走らされているようだった。
諦めて坂の手前でバイクを停める。
エンジンを停止させヘルメットを脱いで地図を確認する。だが、やはり一本道だ。地元の者が使う山へと入る道らしきものはあったが、舗装もされずおよそ車両が通る道とは思えない。
何度確認しても答えは変わらず、気づくと周囲の明るさは失われていた。
完全に陽が落ちてしまったら何も見えなくなると思っていたが、予想に反して月明りが辺りをぼんやりと照らし真っ暗闇とはならなかった。目が慣れただけだろうか。日中あれだけ薄暗かった山の中でも案外こんなものなのかもしれない。
「――立ち往生け?」
背後からのしゃがれた声に体が硬直する。振り向くと、そこには頭巾姿の老婆が佇んでいた。
「あ、いや、道に迷っちゃって……」
驚きで声がうまくでない。なんとかひり出すように返答する。
「あっちの街までは遠いで」
老婆は後ろ手によたよたとバイクに寄ってきて、バッテリー残量を確認したのかそう口にした。手ぬぐいなのか頭の白い頭巾でその表情はよく見えない。
「そうなんですか……。困ったな」
平静を装ってはいたが、この状況をまだ受け入れられずにいる。
老婆はこちらを向き覗くようにしたあと、すっと顔をそらす。怪しいやつじゃないのか顔を確認したのだろう。それにしては、なんだか上の方をみていたような気もするが。
「うちげにバッテリあるで寄ってけな」
そう声を張る老婆は、よたよたと歩き出す。
「あ、でも……」
返答も聞かず先に行ってしまう。その老婆の後ろ姿をしぶしぶついていった。
道沿いを少し歩くと山へと分け入っていく。
か細く傾斜もそれなりにある山道に苦戦しながら老婆の後を追う。足元は枝や石ころが転がるおよそ歩くには不向きなところを老婆はしゃんしゃんと登っていく。
先程までよたよたと頼りない老人特有の力のなさから一変し、まるで別人になったかのように力強い足取りだ。
息切れして足が重い。必死に追うも老婆の後ろ姿はむしろ遠のいていく。
どこまで登るのか。あの後ろ姿を追って大丈夫なのか。不安が募る。
老婆の姿が見えなくなった。開けた場所に出たのだろう。そこまでたどり着くと、ようやく人家が現れた。
昔ながらの簡素な家、瓦屋根に一部はトタン板、石の上に置いただけの木製の柱と基礎の上にのったまだ新しい柱が混在しているような様相が違う家屋が組み合わさっている。古い家を何度も手直ししながら住んでいる様子がみてとれる。
老婆は軒先で農具などを立てかけていた。
「お邪魔します……」
そう改めて挨拶すると老婆は手招きし家へと招き入れる。
線香の匂いのする土間に入ると老婆はいそいそと奥へと消えていく。
「すこし休んでけな? にっころあっから」
老婆の声が聞こえ、何かを用意してくれるようなこと言う。
バッテリーだけを借りたいが、そうもいくまい。諦めて待つことにした。
「ほれ、遠慮すんな」
大皿いっぱいにイモの煮付けを持って老婆は戻ってくる。
「ありがとうございます。いただきます」
そういってイモをつまんで食べた。醤油やみりんで煮付けただけの味だが穏やかで優しい味だ。
「ゆっくりしてげな。いまバッテリ探してくっから」
そう言い残し老婆は再び奥へと消えていった。
しばらくイモをつまみながら待っていると、奥からプラスチックの黄色いカゴを持って来る。
その中には大量のバッテリーとケーブルがごちゃごちゃと乱雑に入っていた。
「こんなに……」
バッテリーがあると聞いてはいたが思っていた様子とは違い戸惑った。10個以上あるだろうか、そう大きくはない農作物をいれるであろうカゴに乱雑に詰め込まれている。さらに他のカゴにまだあるような素振りだ。
「どれか合うべ。まだ、あっから」
老婆は自慢げにバッテリーたちを取り出し始める。並べられたバッテリーを確認すると、かなり古いものも混じっているのに気付いた。比較的新しいものを取り出して規格と残量を確認していく。
「これとこれ、借りていってもいいですか」
適当に見繕って、念のため予備も借りていくことにした。
「あったけ。電気大丈夫か。そこで入れてけ」
老婆の指さした先には古いコンセントがあった。カゴの中にあった変換コネクターを使い充電をさせてもらうことにする。
その間に老婆の昔話に付き合い、1時間ほど過ごして山を降りた。
再びバイクで走りだしたものの、やはり峠から抜けられない。
ライトの照らす道は似たような景色ばかりでいっこうに変わらず同じ登り坂、同じカーブ、同じ下りを繰り返している。
山間の峠道、似た景色にはなるだろう。まして目のきかない夜間の峠……、だが、あまりに似すぎている。
間違いなくループしている。そう観念して認めた。
決定的なのは、あの老婆の家にいく山道だ。もう数回は目にしている。最初は似た山道かと思ったが注意深く観察しても全てが同じだ。これが違う場所だというのは無理がある。
バイクを停め、ひと息つく。
端末を取り出すが通信圏外と表示され、時間表示もこの峠に入った頃の午後3時を示している。数字は進んではいるが気づくと戻って、また3時辺りから時を刻み始めているようだ。
また、息を吐く。
うっすらと白くのびる息をみて、急に寒くなってきたことに気づく。
いったん引き返すか。そう思案していると――。
「なんさ、まだここにいんのか。帰りけ」
薄暗い道端にあの老婆が現れる。白い頭巾だけがぼんやりと浮かび、その表情はみえない。
「なんか道なり進んでるだけなんですけど、また迷っちゃって……」
「もう遅いから泊まってけ。イノシシめがちょろちょろすっから危ねえべ」
そう老婆はいうと、こちらの返事も待たずに歩き出そうとする。
「――あの、バイクここに置いても大丈夫ですかね……」
老婆にそう尋ねると振り向いて山の方向に対して腕をあげ、そこに停めろと指をさす。老婆の家にいくための山道の横にバイク1台くらいを置けるようなふくらみがあった。
バイクをおしてそこに停める。この先は沢になっているのか水音がし、一気に急斜面になっているようだ。バイクが落ちないように少し余裕をもった位置に直してから老婆の後を追う。
2度目になる山道を登っていく。
老婆の姿はもう見えないかと思ったが見上げるとこちらを向いて待っている。登ってくる姿を確認すると、また歩き出しその姿はすぐに小さくなっていった。
重い足をなんとか動かして老婆の家へとたどり着く。
老婆の姿はみえないが、あの土間に入ると匂いが漂ってくる。夕食の用意をしていたのだろうか。何の匂いかはわからない。油とこげ、肉を焼く匂いかもしれない。
「ほれ、あがれな」
奥から現れた老婆にうながされるまま土間から畳の部屋へとあがった。
部屋にはこたつ、テレビ、仏壇、背の低い食器棚が置かれ、こたつの上には新聞とリモコン、茶菓子なのか一口サイズに包装され羊羹と、粉がまぶされた色鮮やかな飴のようなものが数個ほどあった。
「お世話になります……」
どこか居心地の悪さを感じながら、そう言葉にすると老婆は「遠慮すんな」と手を振り、また奥へと消えていく。隣は台所のようだ。
しばらく古い時代劇がうつるテレビをみながら時間をつぶす。
「ほれ、いっぱいくいな」
老婆は大皿に盛りつけられた野菜と肉の炒め物をもってきてテーブルへと置く。
「ありがとうございます」
次いでご飯が山盛りで運ばれ、飲み物は小瓶に入った栄養ドリンクを2本も渡される。
いただきますと食べ始めると、その量の多さに圧倒された。食べきれるのか、そんな不安がよぎるほど肉がたっぷりと入っている。
口に含むと豚肉のようだが、ちょっと違う気もする。たぶんイノシシの肉だろう。豚肉に近い感じで香辛料が効いて美味しい。
「うまいべ。この山で獲れたやつだ」
台所からひょっこりと顔を出した老婆がいう。その顔は嬉しそうだ。ひさしぶりの客人を前にはりきっているのだろう。これは残すことができなそうだ。
覚悟を決めて無理くり食べ終わるまでの間、老婆はずっと動き回り席につくことはなかった。気まずい話をしなくて助かったと思う反面、いったい何をしているのかと気になっていた。
台所と他の部屋、ときに外へと出ている様子だ。
食べ終わった皿を片付ける体で台所へ入る。洗い場には桶と土のついた野菜、使い古されたやかんや鍋の類が並ぶ。床には段ボールや新聞紙にくるまれた収穫物が収まっている。皿をさっと水で流し、その場に置いて戻った。
手持ち無沙汰になったこちらに気づいた老婆は近づいてくると、タオルと石鹸を手渡してきた。
「風呂入れ」
ぶっきらぼうにそう言うと外へと案内される。
家の裏にあった離れ屋に通されると布団が敷いてあり、その奥には洗濯と脱衣所スペース、そして風呂場があった。
来客用の離れ屋だろうか。小さな旅館の一室のように整えられている。どんな場所に寝かされるのか心配だったが、これを見て少し安心した。
「んじゃ、腹減さへったらあっこに入ってから」
老婆が指さす先には小さな冷蔵庫があった。小腹が空いたら、これで満たせということらしい。それだけ言って老婆は戻っていった。
あっさりと宿だけ提供してくれたことに感謝しつつ風呂へと入る。
大昔の薪で沸かす風呂かと思ったが電気式ヒーターのようだ。追い焚きというボタンを押して大人しく待つと徐々に温度が上がってくる。手でかき回して温度を均一にしながら、ここまでに至る経緯を思い返す。
その昔に首都圏に労働力を供給するため街、ベッドタウンと呼ばれたI県K市に行くためにバイクを走らせていた。理由は特にない。とにかく目指せといわれただけだ。
それが途中の峠道、地元の人間には『中山峠』と呼ばれる場所で立ち往生するはめになった。
一本道であるはずの中山峠だったが、走っても走っても峠から抜け出すことが叶わずにいる。複数の山にまたがっているとはいえ距離にしてせいぜい8kmもないはずだ。それをまだ陽があった時間から、夜になるまで走っても抜け出せずにいる。
どこからどこまでなのか、はっきりとはわからない。だが、この中山峠がループしていると認めるに至った。
風呂場の外の様子は静かなままだ。
出られない峠――、おかしな現象はあるものの他に変わった点はない。強いていえばここの主である老婆が親切過ぎるくらいだろうか。見ず知らずの相手に物を貸し、食事を振舞い、宿を与える。だが、ここは田舎だ。都会の薄情な世界の常識とは違うのかもしれない。
とりとめなく考えを巡らすもまとまらなくなってくる。長湯し過ぎた。
ぼーとしたまま風呂を出て敷かれていた布団に横になる。脱いだ上着から端末を取り出し確認するが相変わらず圏外のままと状況は変わっていない。
明日は来た道を戻ってみて、それでも出られないならそのときは――。その辺りで意識が途切れた。
目が覚めると手にしていた端末が震えている。
はっ、と確認するとアラームが起動しただけだった。設定した覚えはない。
なんだと身を起こそうとすると違和感に気づいた。体が重い――、異常に重い。それだけでなく頭の方もモヤがかかったように気持ちの悪い感覚がまとわりつく。
睡眠薬――、とっさに思いついた言葉。
再び体を起こそうと試みて、なんとか上体を起こした。
布団の上でフラフラとする頭をなんとか制御しようと呼吸を整える。外の様子から、まだ時間はそう経っていないことを察した。あのアラームがなければ起きることはなかっただろう。
意識的に呼吸を繰り返し、なんとか立ち上がる。
鉛のように重い体を引きずってドアの前まできた。その外の様子をうかがいながら、そっとドアノブを回していく。
居ない――、そう安堵し外へ出る。
母屋の方を見ると明かりがついていた。あの老婆は起きている。その事実に足がすくむ。
物音をたてないようゆっくりと母屋に近づき様子をうかがい窓からそっと覗き込むが、老婆の姿はない。
こたつテーブルの上には新聞紙が広げられ、黒ずみの目立つまな板、やたら刃の部分が大きい包丁と小さな包丁、砥石、細い金属製の串が並べられている。すぐそばには大型のクーラーボックスも置かれていた。
何かを解体するつもりなのか。嫌な想像が頭をよぎる。
ともかく今はここを離れようと動き出したその矢先――。
「どこさいったー!」
あの老婆の声が響く。さして大きくはないはずの声が夜の林へと響く。
離れ屋の方からだ。
恐ろしくなって逃げ出した。満足に動かない足で、あの山道を転がるように下っていく。何度も振り返っては、あの老婆が追ってきてはいないかを確認する。振り返るたび包丁をもった老婆、いや鬼婆がいるのではないかと恐怖する。
ようやく山道を下り終えて荒い息のままバイクの元へとむかう。
だが、そこにあるはずのバイクがない。
見回すまでもなく、ここになければならないのだ。端末を取り出しセキュリティ機能でバイクの位置を確認する。
表示された位置は、この場所――。
どこか遠くに持ち去られた可能性はなくなった。ともすればと、バイクのあった位置の少し先の急斜面を覗き込んだ。
目を凝らすも暗くてよく見えない。
端末のライト機能をオンにして照らしてみると、斜面の途中に引っかかるようにバイクはあった。落とされた――、そう思った視線のさらに先にも反射する何かがある。それはバイクのようにもみえた。あの大量のバッテリーはここから集めたものか。では、その乗り手たちは……、最後に見た光景を思い出す。
「ここにおったかー」
振り向くと、あの老婆がいる。
頭巾姿ではなく、肩まである長い白髪をおろした姿でそこにいる。その手には包丁が握られ暗い世界でにぶい光を放っていた。
「あぶねーべよ、そん先は沢になってるけー」
そういって老婆はにじり寄ってくる。
心臓の脈打つ音が体いっぱいに広がり、手足の震えが抑えられないほど大きくなっていく。これ以上は耐えられない。覚悟を決め、にじり寄ってくる老婆にむかって声をあげた。
「あなたが当社と締結した仮想現実の提供を含む総合的サービスの契約に関して、利用規約の違反の可能性があることをお知らせいたします」
精一杯の声を出し、そう伝える。老婆の足は止まった。
「契約者および契約内容について21件の重大な確認事項があり、通告を受けてから2週間以内に指定のカスタマーサポートへ申し出てください。対応が取られない場合は、仮想現実サービス提供者の権限において退去措置がとられる場合があります」
さらに続けて、
「なお、通告に際し第三者機関を経由する場合にも、個人情報保護の観点により通告者およびカスタマー従事者には業務に必要ない情報は与えられておりません。当社は、契約者の皆様がサービスを安全かつ適切に利用できるよう、法令遵守を徹底してまいります――」
口早に定型文を投げかける。
老婆は理解したのかしていないのか、ただ立ち尽くしていた。
「おつかれさま~。大変だったね」
事務所に帰ると、ナナオさんが座ったままこちらをむき労ってくれる。
「はい、かなり時間かかっちゃいました。すごいこわかったし」
「こわかった? どんな風に?」
「なんていうか、昔話とかの人喰い鬼婆の話みたいな感じです」
「いいな~、貴重な経験じゃん」
他人事のようにいうナナオさんだが、実際に経験したら大騒ぎしてるはずだ。「辞めてやる」とか「労基にチクってやる」とか大暴れしているのが目に浮かぶ。
「モニタリングはできてなかったんですか? ずっと連絡とれないし」
「できたけど、圏外にして泳がせておけって、所長が」
「えー、なんですかそれー」
「再現性を高めるためだってさ。文句なら所長にいってよ。早く報告書だしてね~」
そうナナオさんは興味なさそうにいって端末をいじりだす。
もう帰りたかったが、しかたなく報告書の作成にとりかかる。
山間にあるループし抜け出せない峠道。そこに住む恐ろしい老婆。できるだけ正確に記していくが出来の悪い怪異の類かオカルト話のようだ。
ほどなく所長が戻ってきた。
「お疲れさま。どうでした? ちゃんと会えました?」
「はい、会えましたけど……」
ことの経緯を所長にかいつまんで説明していく。
「ふむ、とりあえず直接会って口頭で通告できたんですから良しとしましょう」
そう所長はいってパンと手を叩く。仕事が完了したことに安心したようだ。
「なんだったんですか、あれは? 不具合ですか?」
「んー、詳しいことはわかりませんが、どうも全国各地に同名の地域があるような場所で似たような事例……、連絡のつかない利用者が出ているようですね。不可思議な現象も一緒に……」
歯切れの悪い物言いをする所長。後ろにいくほど声が小さくなっていく。
「その不可思議な現象ってやつを聞かされてないんですけど」
誤魔化されず、そう指摘する。
「いやー、知らない方が再現性が高いんじゃないかと思って。まあ、上手くいったんですからいいじゃないですか」
「よくありませんよ。なんとなく察しはついてましたけど……」
送り込まれた時点で何かあるとは思っていた。
「でも地形がループするとか。そんなことあったらすごい大事になるんじゃ……」
「それがなかなか発生するわけじゃないみたいで、うちに依頼が来る前にも方々で試したみたいですけど上手くいかなかったようですね。その点でうちのエージェントは流石ですよ」
そう褒めて誤魔化そうとする所長。何がエージェントだ。
「不可思議な現象が起こらないと、あのお婆――、利用者に会えないってことですか?」
「んー、それは何とも。デベロッパー側なら直接やり取りできるはずですが、仮想世界の権利は個人情報保護と複雑に入り組んでいてそう簡単にはいかないようです」
「つまり仮想世界内で接触する必要がある、と」
「他にも方法はあるんでしょうが、その方が安上がりなんでしょうね」
所長は、やれやれといった手振りで話す。
「あの峠、中山峠っていってましたけど、他にも同じ名前の場所がたくさんあるからおかしくなっているとかですかね」
「その可能性は高そうですね。中山峠なんて全国に何カ所あるかわからないくらいで、場所がら地形も似通ったところですからね。他にも茶臼山という場所でも報告があるようですし。まあ、我々が考えることではないですけど」
所長は、そういってデスクに座る。
「あの利用者の奇行は? 通報しないんですか?」
襲われたことに対して無反応であるのは置いておくとしても仮想世界とはいえ犯罪にあたるはずだ。
「……それ本当に奇行だったんですか?」
「だって、なんか薬を飲まされて、バイクも落とされた上に包丁持ってたし……」
「んー、どれも証拠がありませんしね。実際に接触してケガに準ずる記録が残っていれば対処もするんですが」
そう所長はいうが単に面倒なことを避けたいだけのような気もする。
「でも、追いかけてきたんですよ。包丁もって」
「夜に出ていったら心配して見に来るのは普通のような……。包丁は何かの作業途中だったからとか。バイクは勝手に落ちたのでは? 安定性の高い場所とは言えないようですし。薬はちょっとした食中毒とかアレルギーとか……」
「えー、そんなことあります?」
所長との認識の違いに反抗しつつも、振り返ってみても確実なものを提示できなかった。
「確かに不可思議な現象が起こっている怪異的な現場でしか出会えないそのお婆さんも何がしかの影響を受けていた可能性はありますけど……。実害がない以上、どうするわけにもいかないですね」
そう所長は結論し、さらに続ける。
「どのみちあのお婆さんは退去勧告が出ているので、あそこを出ることになるはずですよ。不採算になる利用者の少ない地域を減らすのが目的のようですし。確認事項うんぬんは名目なんでしょう」
所長の言葉に、あの老婆の行く末を案じてしまう。
「確かに、いまは仮想世界サービスが乱立し過ぎて過疎化が進んで地域でのサービスが滞って高齢者が困っているってよくニュースになってますね」
所長の見立ての方が正しいなら、お世話になったのに礼もいわず帰ってきてしまったことになる。
「仮想世界移住を推進するための政策が拙速で、各所で問題が噴出しても対応が後手後手のようですし」
「75歳以上は移住費完全負担、永久住居権+10000時間のクリエイションメイドつきとか、あきらかに高齢者を騙すような詐欺くさいサービスまで堂々と出回ってたりしてるのみると、なんか末期だなーって思いますよ……。いくら今の高齢者が無料サービスに慣れた世代だとしてもひどくないですか」
「なりふり構わない過剰な付加サービスにも規制が入りそうですけど、結局はいたちごっこになりそうですね」
そんな危うい時勢に不平をたれつつ所長と話し込んでいると、奥にいたナナオさんの声が聞こえてくる。
「所長~、依頼がきたよ。次は地方都市のマンションだって。存在しない部屋が出てるとかなんとか。受けていいよね~」
所長の確認を促す声だが、たぶん事後確認だろう。そして、その仕事をあてがわれるのは決まってる。
「はぁ、怪異の次は都市伝説か……」
次の仕事に悪態をつきながらため息もつく。
「面白いじゃないですか。仮想空間に現実に囁かれた不可思議が自然発生しているんですから」
「発生するまで何度も同じことを繰り返す身にもなってくださいよ。こっちがおかしくなりそう」
嬉々として話す所長にそう反発する。
「ふふふ、不可思議を追う青年が、不可思議に憑りつかれていく――。これも自然発生する怪異の要素を秘めてますね」
それを楽しみ不気味にほほ笑む所長の姿こそ怪異に思えてしょうがない。
こんな場所で働くんじゃなかったと、己の不運と運命を呪うのだった。
中山峠 完?
作 ちよまつ(20210312)
(現在地:短編/中山峠)